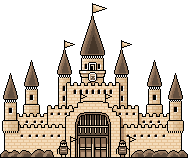<ぶらり岩清水八幡宮>
京都府八幡市の男山に鎮座する石清水八幡宮。
旧称は「男山八幡宮」
男山は、京の都からみて裏鬼門(西南の方角)にあります。
(京都の裏鬼門を守る神社、石清水八幡宮)
石清水八幡宮は、伊勢神宮、京都の賀茂社(上賀茂・下鴨神社)
と並ぶ日本三社の一社です。
また、全国の八幡宮の中でも宇佐八幡宮、鶴岡八幡宮とともに
日本三大八幡宮の一社に数えられます。
歴史的にも昔は二十二社(上七社)に選ばれたり、
旧社格では官幣大社に選ばれたり、
とにかく重要視されていた神社です。
平安初期に、宇佐八幡宮の八幡神から
「都に近い男山に移座して国家を鎮護しよう」
と託宣(神のお告げ)があったので、
この地に勧請したのが始まりです。
都の鬼門を守る比叡山延暦寺と共に裏鬼門を守るため、
王城鎮護の神様として朝廷から篤く尊崇されたことから、
伊勢神宮に次ぐ第二の宗廟と称されてきました。
更には源氏の中で英雄視されている源頼家は
ここで元服の式を挙げたことから
「八幡太郎義家」と呼ばれています。
その後、源氏から篤く崇敬されていて、
源頼朝は鎌倉に幕府を開く際に、
石清水八幡宮から八幡神を鎌倉に勧請しています。
それが鶴岡八幡宮です。

※久しぶりにリフレッシュできました!
|

頓宮 |
頓宮というのは、仮の宮のこと。
普段は何もありませんが、
年に一度の勅祭「石清水祭」で、
山上の御本殿より
御神霊が御遷しされる重要な場所。 |

南総門 |
本殿が参道から真正面ではなく、
ちょっと西側にずれています。
参拝した後に八幡大神様に
真正面に背を向けて帰らないように
中心を外して作っているのだそうです。 |

本殿 |
現在の社殿は江戸前期の
寛永11年(1634)徳川家光による修造

八幡造(切妻造)
(本の中ほどを開いて伏せた形の屋根) |

若宮社
|
若宮社には、
御祭神の八幡大神(応神天皇)の皇子
である仁徳天皇が祀られています。
二階建になっている珍しい摂社
男性の守護神
|

若宮殿社
|
若宮殿社には、
御祭神の八幡大神(応神天皇)の
皇女が祀られています。
二階建になっている珍しい摂社
女性の守護神
|

摂社(住吉社)・末社(一童社)
|
神社の境内にある
小さな社は摂社・末社といいます。
摂社、末社も本社に附属する神社ですが、
現在では特に両者を区分する規定はなく、
本社の管理下にある
小規模神社の呼称として用いられています。
|

築地塀
|
本殿と摂末社を含めて、
築地塀という塀で囲まれています。
珍しい塀ですが、
これは織田信長が好んで使っていたようです。
瓦と土がミルフィーユ状になっていて、
鉄砲の銃撃や耐火性、耐久力に
優れているそうです。
そして本殿の東北の方角、
つまり鬼門に当たる場所は
このようになっています。
|

東総門 |
三つの門はすべて江戸時代前期に
作られたもので三方に配置され、
それぞれ「東総門、西総門、北総門」
と呼ばれ重要文化財に指定されています。
北の回廊は真っ直ぐ伸びて
東側の回廊とは
直角に交わらないようになっています。
これは鬼門(北東)方向の鬼門封じのためで、
鬼門に対して斜めになるように
設計されています
|

一ツ石
|
この石は勝負必勝・勝運の石
とも言われていて、
昔はこの石が走馬・競馬の
出発点だったそうです。 |